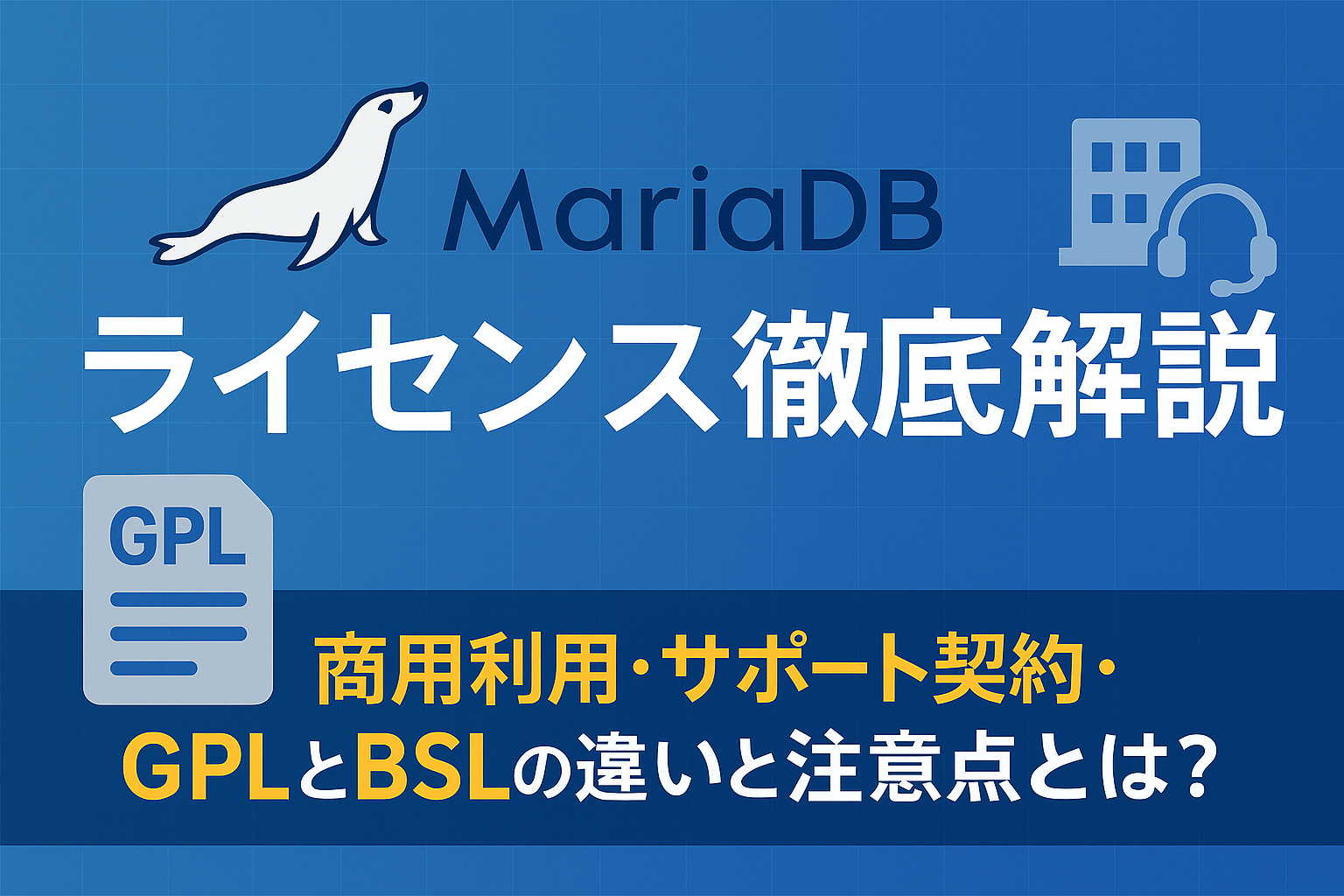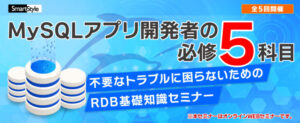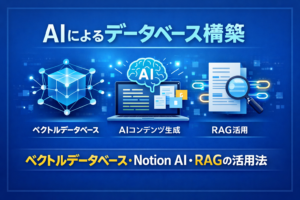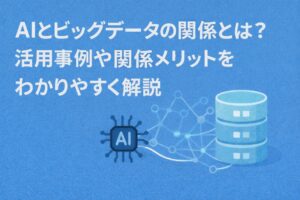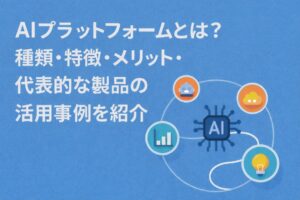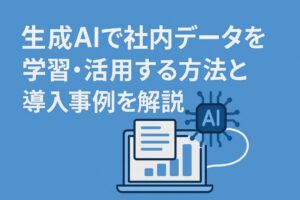そもそもMariaDBとは?オープンソースDBの基本理解
MariaDBは、世界中で幅広く利用されているオープンソースのリレーショナルデータベース(RDBMS)です。名前だけ聞くとMySQLと似た印象を受けるかもしれませんが、それもそのはず。MariaDBは、MySQLから派生して誕生したプロジェクトなのです。
この分岐には、歴史的な背景があります。かつてMySQLは、スウェーデンのMySQL ABという企業によって開発されていました。しかし2008年、MySQLの開発元であるMySQL ABはSun Microsystemsに買収されました。さらに2010年、Sun MicrosystemsがOracle社に買収されたことで、MySQLの開発体制はOracleのもとへと移ることになりました。
Oracleといえば、自社で商用向けの高性能なデータベースを提供しているグローバルIT企業です。MySQLがOracleの傘下に入ったことで、一部のオープンソースコミュニティでは、「今後の開発方針がどのように変わるのか」「MySQLのオープン性が維持されるのか」といった懸念が生まれました。
このような懸念を受けて、MySQLの創始者であるMichael “Monty” Widenius氏が立ち上げたのが、MariaDBプロジェクトです。彼の娘の名前にちなんで命名されたこの新しいデータベースは、「MySQLの精神を守る」ことを目的にスタートしました。つまり、MariaDBは単なるコピーではなく、自由で透明性のある開発体制を引き継ぎ、オープンソースとしての信頼性と進化を重視した選択肢として生まれたのです。
現在、MariaDBは主に2つの形で提供されています。ひとつは、誰でも無料で利用できる「Community Server」です。こちらは従来通りのGPL v2ライセンスで提供されており、オープンソースらしい自由な使い方が可能です。そしてもうひとつは、企業向けに商用サポートを含む「Enterprise Server」。こちらは有償で提供され、信頼性やセキュリティ、SLA(稼働保証)といったビジネスニーズに対応した機能やサービスが含まれています。
このように、MariaDBは無償利用の柔軟性と、法人向けの手厚いサポートの両立を目指した製品設計となっており、個人開発者から大手企業まで、用途に応じた選択が可能なデータベースです。
MariaDBのライセンス体系の違いを理解しよう【GPLとBSL】
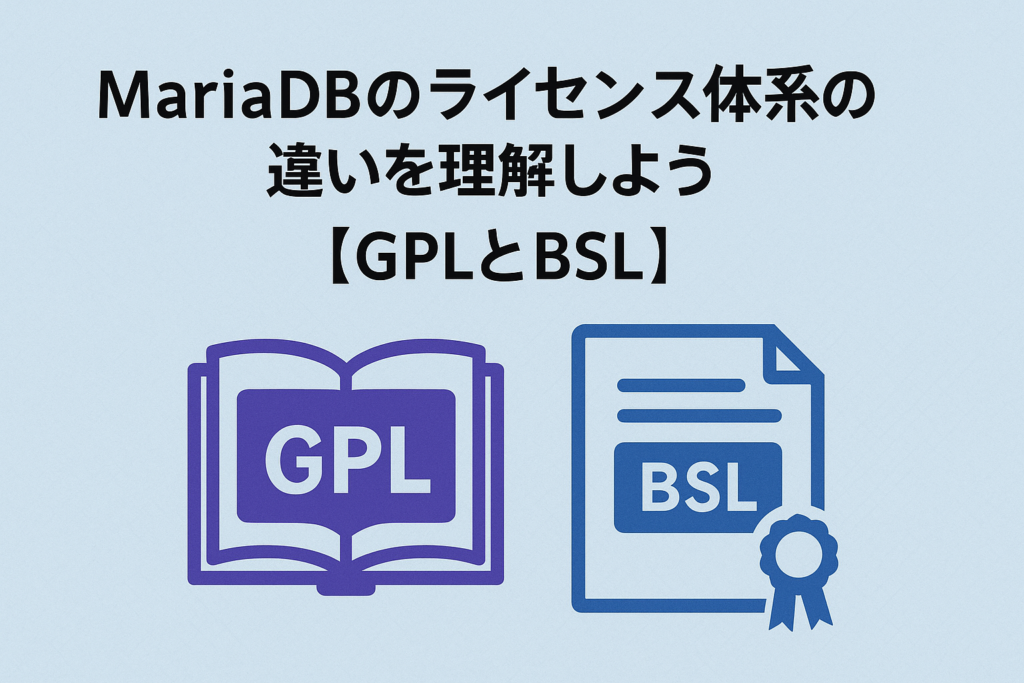
MariaDBはオープンソースであるがゆえに、利用する上でライセンスの理解が非常に重要になります。特に、企業が商用サービスや製品に組み込んで利用する場合には、「GPL v2」と「BSL(Business Source License)」という2つのライセンス形態の違いを把握しておく必要があります。
まず基本となるのは、MariaDBの無償版であるCommunity Serverに適用されている「GPL v2(GNU General Public License Version 2)」です。このライセンスは、ソフトウェアの改変・利用・再配布が自由に認められる一方で、再配布時には「同じGPLライセンスでソースコードも公開しなければならない」という“コピーレフト”の原則を持っています。つまり、自社の製品にMariaDBを組み込んで販売するようなケースでは、ソースコードの公開義務が生じる可能性があるのです。
一方で、社内システムやSaaSのバックエンドとしてMariaDBを使う分には、基本的にこのライセンスによる制限は受けません。ソフトウェアの再配布ではなく、単に内部利用するだけであれば、GPLライセンスにおける「公開義務」は発生しないと考えられています。ただし、このあたりの線引きはケースバイケースであり、利用形態によっては注意が必要です。
近年、MariaDB社は一部の周辺コンポーネントに対して「BSL(Business Source License)」という新たなライセンス形態を導入しています。このBSLは、従来のオープンソース(GPL)と商用ライセンスの“中間”にあたる位置づけで、商用利用に一部制限を設けつつ、一定期間後にGPLなどのオープンライセンスへ切り替わるというユニークな特徴を持っています。
注意が必要なのは、MariaDB Server本体にはこのBSLは適用されておらず、従来通りGPL v2で提供されていることです。BSLが適用されているのは、MaxScaleやColumnStore、といった一部の高度な機能・周辺コンポーネントのみです。
たとえば、MariaDB ColumnStore や MaxScale など、高度な機能の一部はBSLの対象となっており、利用には一定の条件が課されます。
BSLのユニークな点は、その制限が「永続的」ではないことです。BSLで提供される機能は、通常4年などの期限が経過すると、自動的にGPLなどの一般的なオープンソースライセンスに切り替わるという仕組みです。このアプローチにより、MariaDB社は新機能の収益化とオープンソースへの貢献の両立を目指しています。
しかし、ここに見落としやすい落とし穴があります。たとえば、ある企業が「MariaDBは無料だから大丈夫だろう」と思って導入した機能が、実はBSLの対象で商用利用にはライセンス契約が必要だった、というケースもゼロではありません。つまり、無料で使っていた“つもり”が、知らぬ間にライセンス違反になっていたというリスクがあるのです。
MariaDBを安全かつ正しく活用するためには、どの機能がどのライセンスで提供されているか、導入前にしっかりと確認することが大切です。特に法人利用の場合は、技術者だけでなく法務部門とも連携し、利用形態とライセンス適合性を確認するプロセスを設けるべきでしょう。
MariaDBは商用利用できる?法務・契約リスクを整理
MariaDBは「無料で使える高性能なデータベース」として広く認知されています。実際、その多くはオープンソースで提供されており、誰でも自由にダウンロードして利用することができます。しかしながら、「無料で使える=商用利用でも何の問題もない」と考えるのは、やや早計です。特に企業での導入に際しては、GPLやBSLといったライセンスに関する理解と確認が不可欠です。
まず前提として、MariaDBのCommunity ServerはGPL v2ライセンスに基づいて提供されています。このライセンスの最大の特徴は、「改変・再配布が自由」である代わりに、「再配布時にはソースコードを同じライセンスで公開しなければならない」という点です。つまり、自社でMariaDBを内部システムに導入して使う分には、基本的にGPLの制限を受けず、無償で利用できます。これは多くの企業が安心してMariaDBを使っている理由の一つです。
一方で、注意が必要なのは以下のようなケースです。たとえば、自社製品やパッケージソフトにMariaDBを組み込み、顧客に提供する場合。あるいは、MariaDBをベースにした独自機能を追加して販売する場合です。これらは「再配布」とみなされる可能性があり、その際はGPLの条件に従い、ソースコードの公開や同一ライセンスでの提供が義務づけられます。企業の中には、こうした義務に対応できず、気づかないうちにライセンス違反となってしまうリスクを抱えているケースもあります。
また、SaaSのようにWebアプリケーションとしてMariaDBをバックエンドに使う場合は、一見するとGPLの制約を受けないように見えます。というのも、ユーザーにMariaDBそのものを提供するわけではなく、あくまでサービス提供の裏側で使っているだけだからです。事実、多くの法務・技術文書でも「SaaSモデルではGPLの影響は少ない」とされています。
しかしながら、ここにも注意点があります。MariaDBの一部機能、特に先進的な技術が採用された新しい機能群には、先述のBSL(Business Source License)が適用されていることがあります。これは、一定期間は商用利用が制限され、その後にGPL等へ移行するというライセンスモデルです。したがって、「無料で使っていたら実はBSLの機能だった」ということに気づかず、商用利用していた場合には、ライセンス違反に問われる可能性があるのです。
このような事態を防ぐためには、MariaDBを導入する際に、可能であれば法務部門とも相談しながら、どの機能がBSL対象か、再配布に該当するのかなどを確認しておくと安心です。
特に商用利用を前提とする場合や不明点がある場合は、早い段階で確認しておくとトラブルを避けやすくなります。
以下に、企業がMariaDBを商用利用する際に確認すべきポイントをまとめた簡易チェックリストをご紹介します。
MariaDB商用利用時の法務確認チェックリスト
| チェック項目 | 回答 | 結論・対応方針 |
| 社内利用にとどまる用途ですか? | ✅ はい | 原則OK。ただし外部提供が含まれる場合はライセンス要確認 |
| ✅ いいえ | SaaSや再販含む場合はGPL/BSL条件の確認が必須 | |
| MariaDBを製品に組み込んで再配布しますか? | ✅ はい | 再配布=GPLによりソース公開義務が発生。商用利用は要ライセンス検討 |
| ✅ いいえ | 再配布しないなら基本OK。ただし社外との共有が発生するなら再確認 | |
| MariaDBのコードを改変・拡張していますか? | ✅ はい | 改変あり=GPLによりソースコードの公開義務あり |
| ✅ いいえ | 改変なしなら制約は少ないが、利用範囲は明確に | |
| BSL対象の機能を使っていますか? (例:ColumnStore, MaxScale等) |
✅ はい | 商用利用にはMariaDB社とのライセンス契約が必要なケース。無料の誤解に注意 |
| ✅ いいえ | Community版機能内であれば原則自由に利用可能 | |
| Enterpriseサポートの導入を 検討していますか? |
✅ はい | SLA・サポート重視なら契約を推奨 |
| ✅ いいえ | サポート不要ならCommunity版でも可。ただし緊急対応は自社責任 | |
| 法務部門とライセンス確認済みですか? | ✅ はい | 問題なし。記録を残しておくとさらに安心 |
| ✅ いいえ | 要注意!早急にライセンス条件を精査・社内共有すべきタイミング |
GPLライセンスはオープンソースの理念を守るために存在するものですが、その一方で商用活用には慎重さが求められます。もし曖昧な点がある場合は、自社内での確認だけでなく、MariaDB社やライセンスに詳しい専門家への相談も検討すべきです。
MariaDB Enterpriseとは?有償サポートの内容と必要性

MariaDBは無償で使えることが大きな魅力ですが、企業利用――特に業務の基幹システムや重要な顧客サービスのインフラとして利用する場合には、サポート体制やセキュリティ、運用安定性の確保が求められます。そうしたニーズに応える形で提供されているのが、「MariaDB Enterprise」です。
MariaDB Enterpriseは、MariaDB社が提供する有償のサブスクリプションサービスで、単なるソフトウェアパッケージではなく、商用利用を前提とした包括的な支援体制が組み込まれています。契約者には、通常のCommunity版では得られない機能・サポートが提供され、特に以下のような企業にとっては大きなメリットがあります。
まず、Enterprise版ではMariaDB社による優先的な技術サポートを受けることができます。問い合わせ対応や障害時のサポートはもちろん、セキュリティパッチの迅速な提供やバグ修正の優先対応など、業務影響を最小限に抑える仕組みが整っています。さらに、SLA(Service Level Agreement)付きの稼働保証も用意されており、ミッションクリティカルな用途にも耐えうる体制が評価されています。
加えて、Enterprise契約を通じて利用できる専用機能も存在します。たとえば、複数ノード構成での高可用性構築を支援するツールや、監視・運用支援のための統合管理機能、バックアップ・リカバリソリューションなどがそれにあたります。こうした高度な機能は、Community版には含まれていないか、あるいはBSLの対象となっていることもあるため、法人利用においては特に契約の価値が高まります。
Enterprise契約を結ぶことで、企業は「使う責任」だけでなく、「継続的なアップデートとセキュリティへの備え」もMariaDB社と分担することができるのです。単なるツール導入ではなく、パートナーシップとしての関係性が構築できるのが、MariaDB Enterpriseの本質だと言えるでしょう。
実際に、MariaDB Enterpriseは数多くの有名企業や大規模システムで導入されています。たとえば、オンライン百科事典のWikipediaは、その大規模なデータベース基盤にMariaDBを採用しています。また、グローバル企業であるSamsungなどの大手メーカーも、ミッションクリティカルなサービスにMariaDB Enterpriseを活用しています。これらの事例が示す通り、MariaDBは単なる「無償のDB」ではなく、エンタープライズ用途にも十分に応えられる信頼性と拡張性を持ったプロダクトへと進化しているのです。
MariaDBは素晴らしいオープンソースDBですが、 ビジネスの現場では「万が一」に備える体制も欠かせません。
商用利用をお考えならSLA保証、商用ライセンス、専用サポート付きのMariaDB Enterpriseなら、安心と成長を両立できます。MariaDB Enterpriseをご検討される場合は以下のページもご覧ください。
▶ MariaDB商用ライセンス(Enterprise)の詳細はこちら
よくある質問(FAQ)
ここでは、MariaDBのライセンスに関して企業の導入担当者や法務部からよく寄せられる質問を、Q&A形式でまとめました。
Q.MySQLとMariaDB、結局どちらを選べばいいのでしょうか?
A. どちらにも優れた点があり、一概に「どちらが良い」とは言い切れません。目的や運用方針によって適切な選択は異なります。
- MySQLは、Oracle社による商用サポートの安心感とクラウド(AWS RDSなど)での幅広い採用実績が強みです。エンタープライズ向けの導入実績も豊富です。
- 一方、MariaDBはオープンソース精神を色濃く残し、開発の透明性や独自機能の進化が魅力です。商用ライセンス契約も比較的柔軟で、スタートアップやオープンソース重視の企業に選ばれる傾向があります。
互換性の違いやユースケースごとの選び方をより詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください:
MariaDBとMySQLの違いとは?どっちがいいか徹底比較。互換性やユースケース別おすすめ解説。
Q.MariaDBを利用する際、BSL対象かどうかを調べるにはどうすればいい?
A.MariaDB公式サイトのライセンスページまたは各機能のドキュメントに明記されています。特にColumnStore, MaxScaleなどはBSL対象になりやすいため、バージョンごとのライセンス表記と併せて確認しましょう。わかりにくい場合は、MariaDB社や販売代理店への問い合わせが確実です。当社もMariaDBライセンスを取り扱っておりますので、ご不明点がございましたら遠慮なくお問い合わせください。
Q.Enterprise契約はどんなときに必要?
A.以下のようなケースではEnterprise契約の検討が推奨されます。
- BSL対象の機能を使いたい場合
- SLA(稼働保証)やサポート体制を確保したい場合
- 高可用性構成や商用システムでの運用が求められる場合
- 製品に組み込む形で再配布を予定している場合
Enterprise契約により、サポートだけでなく、商用ライセンス下で安心して運用できる環境が整います。
まとめ|MariaDBライセンスのポイントと、導入判断のポイント
MariaDBは、高性能かつ柔軟に使えるオープンソースのデータベースとして、幅広い開発者や企業に支持されています。特にCommunity Serverであれば、無償での利用も可能であり、多くのシステムに手軽に導入することができます。
しかしその一方で、利用形態によってはGPLやBSLのライセンス制約を受ける場面もあります。社内システムでの利用であれば問題ないことが多い一方で、製品への組み込みや、外部提供を含む形態では法的な配慮が欠かせません。「無料で使える」という言葉に安心して飛びつくのではなく、自社の使い方がライセンス上問題ないかを冷静に判断することが求められます。
もし少しでも不安がある場合は、社内の法務部門と連携し、使用ライセンスの確認を徹底しましょう。また、必要に応じてMariaDB社との契約やサポートサービスの活用を検討することで、ライセンス違反のリスクを回避し、より安全・安心な運用環境を構築できます。
技術的な観点だけでなく、法務・経営の視点を持ったライセンス選定が、企業としての信頼性と持続的なシステム運用を支える鍵となります。
もし、MariaDBに関してサポートやエンタープライズ利用をご検討中なら、当社(株式会社スマートスタイル)にご相談ください。
当社は、MariaDBライセンス再販を行う正式な販売パートナーです。また、MariaDB を利用するお客様向けに、幅広いコンサルティングとサポートを提供しています。

オープンソースの自由さと、エンタープライズ品質の安心。
どちらも手に入れて、MariaDBをもっと戦略的に活用しませんか?
本格的なサポート・SLAを確保したい方へ
→ MariaDB商用ライセンス(Enterprise)を見る
OSS版でも確実な障害対応・運用支援を求める方へ
→ オープンソースDBサポートを見る