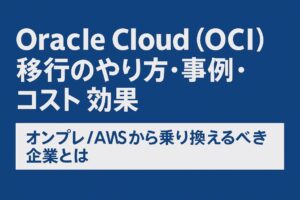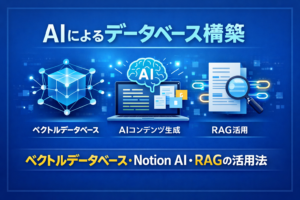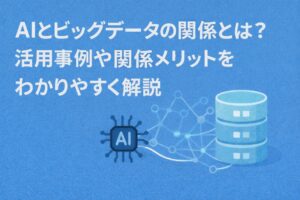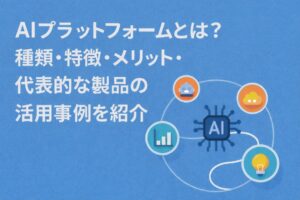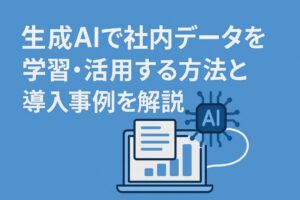本記事では、Azure Database for MariaDBの廃止理由や今後のスケジュール、影響を受けるユーザーが取るべき行動、推奨される移行先や具体的な移行手順について詳しく解説します。適切なサービス選定と計画的な移行が、安定したシステム運用継続のカギです。
1. Azure Database for MariaDB 廃止の概要とスケジュール
1.1 廃止の正式発表日と今後のスケジュール
Microsoftは「Azure Database for MariaDB」のサービス廃止を正式に発表しました。この発表により、同サービスの新規インスタンス作成が一定時期をもって停止され、最終的には既存ワークロードも稼働できなくなるスケジュールが定められています。特に、ビジネスにおいて本サービスを利用している場合は、計画的な代替サービスへの移行が求められます。
以下に、廃止に関連する主なスケジュールを表にまとめます。
| 日付 | イベント | 注意点 |
| 2023年9月25日 | サービス廃止の正式発表 | Microsoft公式ブログ・ナレッジベースに発表 |
| 2025年9月19日 | 完全廃止 | 既存サーバーもすべて停止・削除。以後MariaDBデータベースへアクセス不可。 |
スケジュールの詳細や追加情報は、Microsoft公式ドキュメントで随時更新されています。
移行期間中は段階的に制限事項が強化されていくため、早めにアナウンスを確認のうえ、準備を進めることが重要です。
1.2 いつまでに何をするべきか(重要なタイムライン)
サービス終了までに対応すべき主な工程は次の通りです。Azure Database for MariaDBに依存する全てのシステムについて、確実に期間内での移行を完了させる必要があります。
| 期限 | 推奨アクション |
| ~2023年12月 | サービス終了にともなう移行方針の決定及び影響範囲の特定。関係者・利用チームへのコミュニケーション開始。現行利用状況や依存アプリケーションの棚卸し。 |
| 2024年6月まで | 推奨移行先(例:Azure Database for MySQL Flexible Serverなど)の調査・検証。データ移行計画の策定と試験移行の実施。アプリケーションとの互換性テスト・修正の開始。 |
| 2025年8月末まで | 本番環境への移行の完了。最終テスト・データ移行。既存Azure Database for MariaDBサーバーの停止および不要リソースの削除。 |
| 2025年9月19日 | Azure Database for MariaDBは完全に廃止され、以後は利用不可能になります。 |
上記スケジュールは事前予告なく変更される可能性があるため、Microsoftの公式発表や管理ポータルの通知を随時確認してください。 また、移行に伴うシステムやサービスの一時停止リスクも念頭に置き、計画的なスケジュール管理が必要です。
2. 廃止の背景と影響を受けるユーザーの確認ポイント
2.1 廃止に至った背景とMicrosoftの意図
Azure Database for MariaDBは、2023年9月にMicrosoftより廃止方針が発表されました。 この決定の背景には、MariaDBに対するMicrosoft側でのプラットフォーム運用のコストや、今後のサポートおよび新機能開発の投資優先度調整が影響しています。
マネージドサービス利用者に対し、より柔軟で高機能な最新サービスであるAzure Database for MySQL Flexible Serverへの統一および、パートナー企業との連携強化を図る狙いも見受けられます。
また、MariaDB自体の開発やサポート体制が複雑化したことや、オープンソースデータベース戦略見直しの一環として、リソースを集中したい意向もあるとされています。
詳細は Microsoft公式発表 も参照してください。
2.2 影響を受けるシステム・アプリケーションの特定方法
廃止による影響は、Azure Database for MariaDBを利用している全てのワークロードおよび関連サービスに波及します。まず、自社システムや業務フローで利用中のデータベースの構成を洗い出すことが重要です。以下の観点で該当箇所を特定してください。
| 確認すべきポイント | 確認方法 | 補足 |
| Azureポータルに登録されているMariaDBリソース | Azureポータル上で「MariaDB」を検索し、利用中サーバーを一覧化 | 複数サブスクリプションやリージョンも対象 |
| 接続先データベース情報(接続文字列・エンドポイント) | アプリケーション設定ファイルから「mariadb」やポート3306の利用箇所を検索 | 環境変数やシークレット管理サービスも確認 |
| 外部との連携・バッチ処理 | データ連携設計書やETLツールの設定内容を点検 | 夜間バッチや定期ジョブも影響対象 |
| モニタリング、アラート設定 | Azure MonitorやLog Analyticsなど監視対象サービスを確認 | アラートクリティカル設定にも注意 |
2.3 まず確認すべきチェックリスト
サービス廃止による混乱や計画遅延を防ぐためには、最初の段階で下記の確認を推奨します。
| チェック項目 | 説明 | 実施担当 |
| MariaDBサーバーの利用有無把握 | 全Azureサブスクリプション上のMariaDB稼働状況を管理部門で確認 | システム管理者 |
| 影響を受ける業務システム特定 | 各業務担当者と連携し、データベース接続先を洗い出し | 業務システム担当者 |
| 契約更新時期・バックアップの状況 | 運用保守担当とともに、契約状況・バックアップストレージの状況を確認 | 運用保守担当 |
| 関連アプリケーションや周辺ミドルウェアの対応状況確認 | マイグレーション時の動作保証や互換情報を確認 | アプリケーション開発者・運用担当 |
| 廃止までのスケジュール把握 | 公式発表や社内ガイドラインで対応期限を必ず認識 | システム管理責任者 |
上記チェックリストをもとに、移行計画の早期策定・影響評価・関係部門との情報共有を進めることが、円滑な対応の第一歩となります。
3. 移行準備のポイントと注意事項
3.1 既存データベースのバックアップと検証
移行作業を開始する前に、必ず既存のAzure Database for MariaDBインスタンス全体のバックアップを取得してください。MariaDBのダンプ(mysqldump)やAzure Portalからの自動バックアップ機能、またはスナップショットを活用し、リストア可能な状態を事前に検証しておくことが不可欠です。バックアップデータの検証も忘れずに行い、特にエンコーディング、文字列の破損、オブジェクト(ストアドプロシージャやトリガ)の復元状況など細部まで確認しましょう。
| バックアップ方法 | 特徴 | 注意点 |
| mysqldump | テキスト形式で全データをエクスポート・インポート可能 | 大容量の場合は時間がかかりやすい |
| スナップショット | インスタンス単位で高速にバックアップ | 他サービスへの直接移行には使いにくい |
| Azure自動バックアップ | 定期スケジュールで自動的に取得 | 復元のタイミングや保持期間を要確認 |
3.2 アプリケーション側の互換性チェック(MySQL vs MariaDB)
Azure Database for MariaDB廃止後は、多くの場合Azure Database for MySQL Flexible ServerなどMySQL系への移行となりますが、MariaDBで利用しているSQL方言・機能やドライバの違いによる互換性問題が発生する可能性があります。アプリケーションから利用しているCRUD処理だけでなく、全文検索、JSON型、システムプロシージャ、プラグイン利用などを洗い出してください。MySQLとMariaDBの違いについては公式のMariaDB公式ドキュメントなどを確認し、必要に応じてコードの書き換えや、互換ライブラリの導入を検討しましょう。
| 互換性チェック項目 | 確認方法 | 推奨アクション |
| 利用SQLコマンド・関数 | クエリログ抽出・grep等 | MySQLとMariaDB差異の洗い出し |
| データ型(例:JSON、ENUM等) | テーブル定義書・スキーマ見直し | 非互換の場合は型変換検討 |
| ストアドプロシージャ等 | SHOW PROCEDURE STATUS等 | MySQL移行後動作要テスト |
| 認証方式・接続ドライバ | アプリケーション設定 | MySQL対応モジュール導入 |
3.3 レプリケーション・ダウンタイム対策
業務へ影響を与えることなく円滑に移行を行うためには、レプリケーションの活用や計画的なダウンタイム対策が重要です。データボリュームが大きい場合やサービス停止が許容できない場合は、MySQLレプリケーションやAzure Database Migration Service(DMS)を用いた段階的な移行を検討しましょう。最低限、ダウンタイム見積もりと業務影響が少ない時間帯での移行計画を立て、必要に応じて一時的なフェイルオーバー構成やローリングアップデートも検討します。
| ダウンタイム削減手法 | 概要 | 適用シナリオ |
| レプリケーション移行 | 旧MariaDBと新MySQLサーバでリアルタイム複製しつつ最終切替のみ停止 | 業務サービスをほぼ止めずに移行したい場合 |
| データベースマイグレーションサービス(DMS) | Microsoftが推奨する専用移行サービスで段階移行サポート | 移行手順で停止時間を最小にしたい場合 |
| 一時停止・メンテナンス移行 | 事前告知し夜間・休日作業でフルバックアップ&リストア | 利用ユーザーが限定・停止許容できる場合 |
4. 推奨移行先:Azure Database for MySQL Flexible Server
4.1 サービス概要と主な機能
Azure Database for MySQL Flexible Serverは、Microsoft Azureが提供するマネージドなMySQLデータベースサービスです。 標準で高可用性(HA)構成や自動バックアップ、柔軟なスケーリング、Azure上のセキュリティ機能(VNet統合、プライベートエンドポイントなど)に対応し、運用管理の負荷を大きく削減できます。また、ゾーン冗長構成や自動パッチ適用、予測可能なパフォーマンスも強みです。
| 主な機能 | 詳細 |
| 高可用性(HA) | ゾーン冗長構成、フェイルオーバーによるダウンタイム最小化 |
| 自動バックアップ | 最大35日間の保持に対応し、ポイントインタイムリストア可能 |
| 柔軟なスケーリング | CPUコア数やストレージ容量を動的に変更可能 |
| セキュリティ | VNet統合、暗号化、Azure AD認証 |
| コスト最適化 | 予約インスタンス・停止と開始によるコストコントロール |
4.2 MariaDBとの互換性と移行上の注意点
Azure Database for MySQL Flexible Serverへの移行にあたっては、MariaDBとMySQLの間の互換性に注意が必要です。 MariaDBはもともとMySQLのフォークであるため、多くのSQL文やストアドプロシージャ、テーブル構造は互換性があります。
しかし、バージョン差異や独自拡張(ストレージエンジン、関数、パラメータ等)によっては一部非互換が生じる場合があります。 例えば、MariaDB独自の機能(Ariaストレージエンジン、Sequenceオブジェクト等)はMySQL側には存在しません。 そのため、 事前にスキーマ、機能、SQL文の移行可否を確認し、必要に応じて修正や調整を実施することが重要です。
| 項目 | 互換性の有無 | コメント |
| 基本的なSQL文 | 〇 | 一般的なCRUD操作は互換性あり |
| ストレージエンジン | △ | InnoDB・MyISAMのみ利用可(Aria等は要変換) |
| システム関数 | △ | 一部関数はMariaDB特有(要代替・検証) |
| パフォーマンス最適化機能 | △ | インデックス・パラメータ設定等は違いに注意 |
公式ドキュメントにも記載があるため、参考にしてください: Azure Database for MySQL Flexible Server のドキュメント
4.3 Flexible Serverを使うメリット(パフォーマンス・HA・コスト)
Azure Database for MySQL Flexible Serverを選ぶ最大のメリットは、高度な可用性と柔軟なパフォーマンス調整、Azureエコシステムとの高い親和性です。
- パフォーマンス:必要に応じてCPUやメモリ、ストレージを動的に拡張できるため、ワークロードの変化に柔軟に対応できます。ストレージも最大で16TBまで拡張可能です。
- 高可用性:可用性ゾーンをまたいだ冗長構成や自動フェイルオーバーにより、RPO(目標復旧時点)やRTO(目標復旧時間)を最小化できます。
- コスト管理:CPUやストレージをあとから調整できるため、つねに最適なリソースで運用が行なえ、停止・再開機能を使って無駄なコストを削減可能です。また、1年・3年予約割引も利用できます。
- 柔軟な運用:自動メンテナンス、バックアップ、セキュリティアップデートにより、運用・保守負荷が大きく軽減されます。
なお、パフォーマンス要件や高可用性、コストに関わる比較検討が必要な場合には、Azureポータルの見積もりツールや公式ドキュメント価格ガイドも活用してください。
5. Azure Database for MySQL Flexible Serverへの移行手順
5.1 ステップ1:MySQL Flexible Serverの構築
まずは、Azureポータルから「Azure Database for MySQL Flexible Server」を新規作成します。構築時にはリージョン、コンピューティングサイズ、ストレージ容量、可用性ゾーンなどの設定を慎重に選択しましょう。特に移行後の安定稼働のためには、「ゾーン冗長高可用性」の有効化や自動バックアップ期間の設定も検討が必要です。
セキュリティ要件を満たすためネットワーク設定(VNet統合やパブリックアクセス制御)および認証情報(管理者ユーザー名・パスワード)の管理も慎重に行いましょう。
| 設定項目 | 推奨設定例 | 注意点 |
| リージョン | 利用中のアプリケーションに近いリージョン | ネットワーク遅延の最小化 |
| 可用性 | ゾーン冗長高可用性 オン | 障害耐性の強化 |
| バックアップ | 7日以上 | 災害復旧に備える |
| VNet統合 | 必要に応じて有効化 | セキュリティポリシーへの適合 |
5.2 ステップ2:データ移行ツールの選定と利用(mysqldump, DMSなど)
データ移行には複数のツールが利用可能です。「mysqldump」「MySQL Workbench」「Azure Database Migration Service(DMS)」の中から、データ量や業務要件に適した方法を選定します。
| 移行ツール | 特徴 | 推奨ケース |
| mysqldump | テキストベースのエクスポート・インポート。シンプルで信頼性が高い。 | 小~中規模データベース、ダウンタイム許容可 |
| Azure DMS | GUIによる簡易操作。大規模データ、オンライン移行対応。 | 大規模DB、ダウンタイム最小化が必要 |
| MySQL Workbench | GUIで直感的操作。限定的なバージョン互換。 | 手動・少量の移行、テスト環境 |
移行元となるAzure Database for MariaDBのデータおよびスキーマ/ストアドルーチン/トリガーなどは事前にバックアップを取得し、移行ツールで検証することが重要です。
また、エンコーディングやSQLモードなど、MySQL Flexible Serverとの互換性に差異がないかも必ず事前に確認しましょう。
5.3 ステップ3:アプリケーション接続切替とテスト
移行作業が完了したら、アプリケーションの接続先を新しいMySQL Flexible Serverへ変更します。この際、接続文字列やユーザー権限、ポート番号(既定は3306)などの設定が正しいか再度検証してください。
本番切り替え前に十分なテスト(データ整合性・パフォーマンス・トランザクション動作の検証)を実施し、予期せぬエラーや互換性問題がないことを確認しましょう。
| テスト内容 | 具体的観点 |
| データ整合性 | レコード数・主キー重複・NULL値チェック |
| アプリケーション動作 | 主要なクエリ・処理の正常動作テスト |
| パフォーマンス | レスポンスタイム・スループット検証 |
5.4 ステップ4:本番移行と稼働後のチェック
十分なテストが完了し、問題が解消されたら本番環境での切り替えを行います。切り替えの際はマイクロソフト公式ドキュメントのガイドラインも参照し、手順漏れを防ぎましょう。
移行後には以下のポイントをチェックします。
- アプリケーションからの新データベースへの接続とクエリ動作
- バッチやインポート処理の正常実行
- 監視・アラート設定(CPU、メモリ、ストレージ使用率、スロークエリなど)
- バックアップの自動取得・リストアテスト
- パフォーマンスや遅延の有無の継続監視
また、移行後数日は運用状況を集中的に監視し、万が一障害や性能問題が発生した場合に迅速にロールバックできる体制を整えておくことも大切です。
6. 他クラウドサービスへの移行という選択肢
6.1 Amazon RDS for MariaDB
Azure Database for MariaDBの廃止を受けて、Amazon RDS for MariaDBへの移行は、多くの企業や組織で現実的な選択肢となります。RDS for MariaDBは、フルマネージド型のリレーショナルデータベースサービスであり、MariaDBの公式サポートを提供し、アップグレードやパッチ適用も自動で行われます。
また、高可用性構成(マルチAZ)、自動バックアップ、スナップショット取得、監視機能も標準で備えています。移行時は、Amazon Database Migration Service (DMS) やmysqldumpツールなどを活用し、ダウンタイムを最小限に抑えることが推奨されます。
6.2 Google Cloud SQL for MariaDB
Google Cloud Platformでは、Google Cloud SQL for MariaDBというサービスが提供されています。Cloud SQLは、MariaDBだけでなくMySQLやPostgreSQLにも対応しているフルマネージド型RDBです。
特長としては、自動バックアップ、フェイルオーバー、Point-in-Timeリカバリ、シームレスなスケーリングに対応しており、Google Cloudの他サービスとの統合連携もスムーズです。
データ移行には、Google Database Migration Service(DMS)や外部バックアップ、レプリケーション機能を利用できます。
6.3 選定時に考慮すべきポイント(コスト、運用負荷、機能)
マネージド型のMariaDBサービスをクラウド上で選定する際は、以下のようなポイントを確認し、業務要件に最適なサービスを選ぶことが重要です。
| 比較ポイント | Amazon RDS for MariaDB | Google Cloud SQL for MariaDB |
| 対応バージョン | 定期的な新バージョン対応、公式サポート | 主要バージョン対応、バージョン切替も容易 |
| 高可用性 | マルチAZ、フェイルオーバー標準対応 | リージョン内レプリカ、オートフェイルオーバー対応 |
| 運用自動化 | 自動バックアップ、パッチ適用、監視 | 自動バックアップ、維持コスト最適化 |
| コストモデル | 従量課金制、リザーブドインスタンス割引あり | シンプルな従量課金、割引プランあり |
| 他プロダクト連携 | 豊富なAWSサービスとの連携 | BigQueryやGKEなどGoogle Cloudとの親和性 |
| サポート体制 | プレミアム/エンタープライズサポート | 有償サポート、24時間365日対応 |
| 移行ツール | AWS Database Migration Service | Google Database Migration Service |
移行先の選定にあたっては、現行システムの特性や運用体制、既存クラウド環境、コストインパクトなど多角的な観点から総合的に判断することが大切です。また、各クラウドベンダーの提供する移行支援プログラムやサポートも活用し、移行プロジェクトのリスク最小化に努めましょう。
7. 移行をスムーズに進めるためのベストプラクティス

7.1 移行計画の立て方と関係者の巻き込み
円滑なデータベース移行を実現するためには、明確な移行計画の策定と、関係者の早期巻き込みが不可欠です。 まず、現行システムの利用状況やデータベースの依存関係を棚卸しし、影響範囲を可視化することから始めましょう。その上で、リスク、作業工数、必要なリソースを明確にし、関係部門(システム管理者、アプリケーション開発者、運用担当者、ビジネス部門など)と緊密にコミュニケーションをとってください。定期的な進捗確認や情報共有の場を設けることで認識齟齬や作業漏れを防止できます。
| ステップ | 主な内容 | 留意点 |
| 1. 影響範囲の調査 | 依存サービスやアプリケーションの洗い出し | 直接・間接的な連携先も含めて調査 |
| 2. タイムライン策定 | 作業工程の計画、必要な期間の設定 | 廃止日から逆算して余裕を持たせる |
| 3. 関係者への通知 | 関係者を把握し、説明会や進捗報告の場を設置 | 移行による影響やスケジュールを明確に伝える |
7.2 データ検証・アプリケーションテストのコツ
移行後のトラブルを防ぐには、徹底したデータ検証とアプリケーションの動作確認が重要です。 データベース移行時は、エンコーディングの違いやデータ型の互換性に起因するトラブルが発生することがあります。データ移行後にデータ件数、データ内容、参照制約やインデックスの整合性を十分に確認しましょう。アプリケーションについては、読み書き処理やトランザクションが正しく動作するか、バージョン差分による非互換がないか入念なテストが必須です。
| 検証項目 | おすすめの方法 | 注意点 |
| データ件数・内容の比較 | 移行前後でSELECT COUNT(*)やチェックサムを使う | 大規模データの場合はサンプリング検証も併用 |
| 参照制約・インデックスの検証 | INFORMATION_SCHEMAテーブルで構造比較 | 意図しない自動変換に注意 |
| アプリケーションテスト | テストケースの自動化(CI/CD)や負荷テストを推奨 | MySQL固有機能への依存がないか要確認 |
7.3 運用開始後のモニタリングと障害対策
移行が完了した後も、安定運用のためには継続的なモニタリングと障害時の対応体制が鍵となります。 Azure Database for MySQL Flexible Serverでは、標準でパフォーマンス監視やアラート機能が利用可能です。CPU使用率や接続数、クエリの実行状況などのメトリックを定期的に確認しましょう。また、自動バックアップやフェールオーバー設定も見直し、障害発生時の影響範囲最小化と迅速な復旧を意識した体制づくりを行うことが肝要です。障害発生時の連絡手順や復旧プロセスも事前に関係者で共有しておくと安心です。
| 運用項目 | 具体的な取り組み | 推奨ポイント |
| システムモニタリング | Azure MonitorやLog Analyticsによる監視 | アラート閾値の設定と定期ログレビュー |
| バックアップ管理 | 自動バックアップスケジュールの確認とテストリストア | 復旧手順のドキュメント化と演習 |
| 障害時対応 | 担当者連絡網、復旧プロセスの事前共有 | SLAを考慮した迅速な対応計画 |
8. まとめ:Azure Database for MariaDB 廃止に向けて今すぐすべきこと

8.1 どの移行先が最適かを早めに判断
Azure Database for MariaDBの廃止が正式に発表された今、影響を受けるシステムやアプリケーションを早急に洗い出し、Azure Database for MySQL Flexible Serverや他クラウドサービスへ移行するかの判断を急ぐ必要があります。
8.2 廃止までのスケジュールを逆算して対応
廃止日までには十分な期間が設けられていますが、計画的に移行作業を進めるため、マイルストーンを設定し、データ移行・検証・切り替えを早めに行いましょう。
8.3 今後の安定運用に向けた体制づくり
新たなデータベース環境での運用安定化を目指し、モニタリングやバックアップなど運用体制の整備、関係者への情報共有を徹底しましょう。これが今後の安定運用の鍵となります。
Azure Database for MariaDBからの移行をご検討なら
Azure Database for MariaDBの廃止は、単なるサービス終了ではなく、システムの安定運用や事業継続に直結する重要な課題です。
「どの移行先が最適なのか判断がつかない」「移行時のダウンタイムを最小限にしたい」「互換性や性能面の不安を解消したい」といった声は、多くの企業から寄せられています。
こうした移行プロジェクトでは、事前の計画立案から環境構築、データ移行、アプリケーション調整、そして移行後の運用監視まで、一貫したサポートが必要です。特にAzure Database for MySQL Flexible Serverなどの新環境に移行する場合、MariaDB特有の設定や機能の差異を正しく把握し、最適化した構成で稼働させることが、移行成功のカギとなります。
スマートスタイルは、20年以上にわたりデータベース運用・構築を手掛け、クラウド移行支援でも豊富な実績を持っています。
Azure Database for MariaDBからの移行においても、影響範囲の調査から移行計画策定、検証、データ移行、本番切替、移行後の最適化までをワンストップで支援します。お客様の要件やシステム特性に合わせた移行戦略をご提案し、安定稼働とコスト最適化の両立を実現します。
廃止期限が迫る今こそ、早めの準備が重要です。まずは現状の利用状況や課題をヒアリングし、最適な移行プランをご提案いたします。
Azure Database for MariaDB移行ならスマートスタイルにお任せください